漢方でとらえる起立性調節障害の治し方
起立性調節障害とは?
起立性調節障害は、自律神経の乱れによって血圧調節がうまくいかず、朝起きられない、立ちくらみ、めまい、頭痛、倦怠感などの症状が現れる病気です。特に思春期の子どもに多く見られます。
このページでは、起立性調節障害の改善に役立つ生活習慣や食事について詳しく解説します。起立性調節障害でお悩みの方の症状が少しでも軽くなるように、治療中の方はより早く治るように日常生活でできる対策を取り入れ、症状を軽減しましょう。
水分摂取と起立性調節障害
水分不足が起立性調節障害の原因?
起立性調節障害の治療では、非薬物療法として水分と塩分の摂取が推奨されます。ガイドラインでは1日1.5〜2リットルの水分摂取が推奨されていますが、すべての患者さんが水分不足であるとは限りません。
なぜ水分・塩分摂取が勧められるのか?
起立性調節障害の症状の一つに「朝の調子の悪さ」があります。これは血圧が低いために起こります。本来ならば朝は血圧が上がっていくのですが、起立性調節障害の方は自律神経の乱れにより血圧が上がりにくく、立ち上がれなくなったり、活動が困難になったりします。
そのため、血圧を少しでも上げるために水分と塩分の摂取が勧められるのです。しかし、本当に水分不足が原因であれば数日間水分をしっかり摂れば治るはずです。1週間以上しっかり摂取しても改善しない場合、水分摂取以外の要因を考える必要があります。
起立性調節障害に水分摂取は必要?
そもそも起立性調節障害は自律神経の問題です。血圧が低いからといって水分で血圧を上げようとしても自律神経を整えないことには全く意味がないのです。
水分摂取で治るものは起立性調節障害とは別のものとして考えたほうがいいのかもしれません。
漢方薬を扱っている病院でも水毒を治す漢方薬を処方しているのに水分を多く摂るようにと矛盾した治療をしているところが少なくないです。
漢方で考える「水毒」と起立性調節障害
水毒とは?
漢方では「水毒(すいどく)」という概念があります。これは、体内の水分代謝が悪くなり、余分な水が体に溜まる状態を指します。
特に起立性調節障害の患者は、胃に水毒があることが多く、水分をいくら摂取しても代謝が悪いために、必要なところに届かず、胃が浮腫んでしまいます。その結果、自律神経の乱れが悪化し、めまいや倦怠感を引き起こすのです。
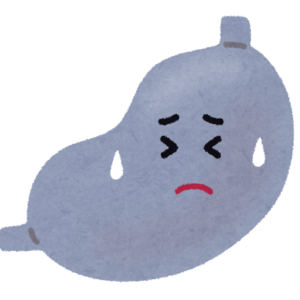
水毒を悪化させないための生活習慣
- 消化に良いものを摂る:よく噛んで胃腸に負担をかけないことが大切。
- 水分の摂取量に注意する:喉が渇いたら飲む程度でOK。
- 冷たい飲み物を避ける:胃を冷やすと水毒が悪化するため、なるべく温かい飲み物を。
- 甘いもの・生ものを控える:胃の機能を低下させる原因となるため。
発散することも重要!
「気の上衝」と起立性調節障害
漢方では「気の上衝(きのじょうしょう)」という概念があり、これはエネルギーや熱が首から上にこもる状態を指します。これにより、のぼせ、頭痛、めまい、気持ちの落ち込みが発生しやすくなります。こもっている気を発散することで気の上衝は緩和させることができます。
気を発散させる方法
- 運動をする:午後の調子が良い時間帯に軽い運動を行い、汗をかく。
- サウナ・入浴:発汗による発散効果はあるが、のぼせやすいので注意。
- 辛いものを食べる:特に香りの強い辛味(シナモン、薄荷、紫蘇など)は気の発散に役立つ。
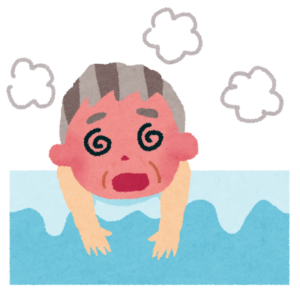
起立性調節障害の生活習慣改善まとめ
- 水分を摂りすぎない:水毒を悪化させないよう注意。
- 胃腸の働きを整える:冷たいもの・甘いものを控え、消化の良い食事を。
- 適度な運動で気を発散する:軽い運動で汗をかく。
- 長湯やサウナはほどほどに:のぼせやすいため注意。
- 香りの強い辛味で気を発散する:シナモンや薄荷などを活用。
起立性調節障害は生活習慣の見直しで改善できる病気です。日常生活でできることから取り入れ、少しずつ体質を整えていきましょう。
さらに詳しい情報・個別相談はこちら
当店では、起立性調節障害の根本改善を目指した漢方治療を行っています。気になる方はお気軽にご相談ください!
